できない理由を探さない。SMFLの自走型・社内共創「DXチーム」がとにかく前向き

「DXの重要性はよく分かっているのだが……」と、大胆な変革に二の足を踏んでいる企業は少なくない。旧習からの変化を嫌う組織の硬直性、心理面での抵抗感などが壁となって立ちはだかる。しかし今やデジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業にとって急を要する経営の重要課題。そこでヒントとなるのが、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の取り組みだ。社内共創型のチーム「イノベーションPT」を設置、全社活動として、DXを推進している。同社のデジタル戦略を牽引するリーダーたちに話を聞いた。
何のためのDXか? モノがデジタル化する未来
コロナ禍で喫緊の課題となったDXへのシフト。しかし、「何から始めてよいか分からない」あるいは「実施はまだまだ限定的」といった“DX途上企業”が全体の9割超を占める――経済産業省が2020年末に公表した「DXレポート2 中間取りまとめ」を見ると、DXの重要性は認識しているものの、その目的設定や体制構築、推進手法に戸惑う企業の実態が浮かび上がる。
そんな悩みに対して大きなヒントを示唆する取り組みが、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)のDX推進チーム「イノベーションプロジェクトチーム(以下、イノベーションPT)」だ。自社における業務プロセスのデジタル化を通して培った知見を生かし、2021年にはモノのライフサイクル管理プラットフォームをリリースする。その真髄は、営業現場とエンジニアの隔たりを取り払い、社内の力を結集させて、開発部門を「完全内製化」する仕組みを構築したことにある。
しかしそもそもなぜ、総合リース会社であるSMFLが「デジタル」に取り組むのだろうか。同社デジタル開発室の室長としてチームを率いる藤原雄は、その意義を次のように語る。

藤原 雄
デジタル化されたモノがもたらす未来とは何か。たとえば、位置情報や稼働時間など、モノから得られた情報を蓄積し、解析・活用すれば、モノが持つ価値は増幅され、そこから新たな価値を生み出すことができる。そう考えれば、リース契約を通じて提供されるモノは、ただの無機物ではない。顧客との結びつきを強化し、ビジネスをステップアップさせる可能性を秘めた「種」だと言えよう。
「データ分析により、特定の機器の利用頻度が継続的に低いことが分かったとします。そこから、リースの見直し、モノの販売、レンタル、シェアを勧めてみるなど、資産を眠らせないための戦略的な提案ができます。モノから得た情報がエビデンスとなるので、提案の説得力も高い。そうやって有機化するモノが増えていけば、新たなビジネスモデル創出のチャンスも増加します。だからこそ、日本最大級のリース資産を保有する我々がデジタル先進企業を目指すのです」(藤原)
独自の強みを発揮して、新たなビジネスモデルの創出につなげる――それが、SMFLが描くDXの姿だ。
トップが数字を示し、経営を巻き込んで組織を動かす
とはいえ、既存ビジネスの改革は、テクノロジーだけで実現できるものではない。業務の効率化やQCD(品質・コスト・納期)の改善が期待できると分かっていても、やり慣れた業務フローが変わることへの現場の不安は大きく、「総論賛成・各論反対」で、変化への動きが鈍るのが常だ。
旧GEキャピタルをルーツとするSMFLキャピタルとSMFLの経営統合が実現した2019年、デジタル開発の精鋭部隊を迎え入れたことを機に、橘正喜代表取締役社長は「デジタル先進企業」を宣言した。トップが強い意志を示したことで、SMFLの社内でも「デジタル」「イノベーション」のキーワードを意識する向きが強まった。
「DXを円滑に進める推進力として、トップの号令は重要です。経営戦略としてデジタル化に取り組む姿勢を掲げ、同時に、ビジョンを明確に示すことで、動きやすい環境の下地ができあがります」
外資系企業でキャリアを積み、効率重視のデジタルシフトが求められる企業風土で揉まれてきた藤原は、そう指摘する。
「どのように変革すべきか。それを判断する手がかりとして、リーダーには具体的なKPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)を示すことが求められます。『顧客満足度を10にする』『コスト8割カット』などのKPIで目標を明確にし、達成に向けてのソリューションを模索するなかで、目指すべきDXの姿が自ずと見えてくるのです。日本企業の中には、『営業目標はあるがKPIがない』本社部門が少なくないと耳にしますが、弊社のデジタルプロジェクトでは、少なくとも生産性に関するKPIを本社部門も設定し、生産性向上によって生みだされた時間をどう使うか、各部がコミットして取り組んでいます」(藤原)
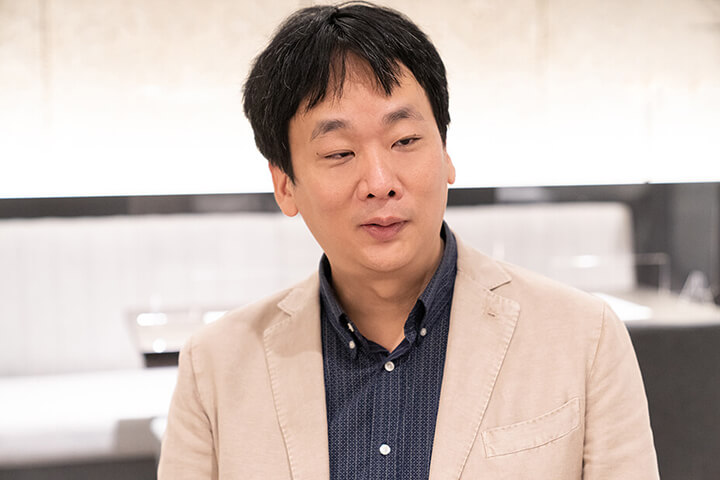
川名 洋平
「イノベーションPTは、役員を巻き込んだ組織です。月次報告会には、30以上の個別プロジェクトのチャンピオン、リーダー、PMO約80名が参加。ありがちな役員報告会と異なるのは、プロジェクトの進捗ダッシュボードに黄信号と赤信号が並んでいることでしょうか。緑信号ばかりだと、逆に役員から心配されるんです。DXは組織変革そのものなので、全てが順調に進むことはありませんよね。むしろ、赤信号がないほうが珍しくて、その場合、問題把握すらできてないのか、課題を役員に上げられない風通しの悪い雰囲気があるのではないかと懸念されます。月次のリズムで、役員が意思決定・問題解決のサポートをするのが特徴です」
「また、トップダウンだけでなく、水平方向に影響力を広げてくれる“支持者”づくりも重要です。月次の役員報告会では、進捗報告だけでなく、エンジニアからAIやIoTを用いた新たな技術の紹介も行われます。それを見た営業・事務・本社部門の社員が活用方法のアイデア出しを行い、会議後すぐに、実際の利用シーンでテストしたり、お客様へのインタビューを通じた仮説検証が行われます」
さらに、RPA推進役を志願した約100人の「RPAアンバサダー」を通じた部単位での業務デジタル化やデジタルリテラシーの研修を通じて、「デジタル」を自分ごと化する意識付けを図っている。
子どもであれ。大きく考えて、小さく素早く始める
DXの本質は、ビジネスに新たな価値を生み出す「ダイナミックな変革」である。それを実現するには、変化を受け入れる土壌づくりが欠かせない。特に重要なのが、未知なる領域への不安からくるネガティブな思い込みや先入観をひっくり返すマインドセットだ。
SMFLでは、DXを推進するにあたって次のような指針を掲げ、実践している。
| Think Big, | 大きく考え、 |
| Start Small, | 小さく素早く始めて、試してみる |
| Scale Fast, | 成功したら、素早く展開する |
| with Ownership and Leadership | オーナーシップとリーダーシップをもって |
えてして、多くの経験を重ねた「大人」は保守傾向が強く、「失敗は避けるべき」「うまくやらなければ」という心理的圧迫を感じやすい。プレッシャーはいつしか創造性を窒息させ、変化や改革の芽を摘んでいく。
だからこそ、と藤原は語気を強める。「子どものようにありたいのです。子どもの挑戦って、けっして『失敗』ではないですよね。むしろ、成長のために欠かせない経験。プロジェクトも同じだと思うんです。臆せずに経験を重ね、たとえ失敗したとしてもそれを糧として挑戦し続けることのほうが、はるかに大事」
大人と子ども。失敗を怖がらないのはどっち?

こうして育まれた「子ども」には、自ずと当事者意識が備わっていく。
「まずは、やってみること。質より量。『デジタル技術はよく分からないので……』と誰かに任せてしまうのではなく、社員一人ひとりが、自らの担当業務をよりよくするにはどうしたらいいかという当事者意識を持って取り組んでいます」
藤原は笑顔で、朗らかに話す。「義務感」を背負った改革にはどこか悲壮感が漂うものだが、藤原からも川名からも、それが微塵も感じられない。「できない理由」を探すのではなく、「実現する方法」を考え、前向きに実装する姿勢を体現している。
走り出したSMFLのデジタル戦略。後編では、具体的なサービスと開発手法について紹介する。
(内容、肩書は2021年3月時点)
お問い合わせ
DX推進部
メールアドレス:









