ベーカー&マッケンジー法律事務所
江口直明(えぐち・なおあき)

ベーカー&マッケンジー法律事務所の再生可能エネルギーグループ所属。太陽光発電・陸上・洋上風力発電・地熱発電などの、再生可能エネルギー関連に多数の実績がある。現在は、蓄電池やコーポレートPPAの、法的実務案件を多く受け持っている。内閣府PFI推進委員会専門委員、国土交通省空港運営のあり方に関する検討会委員、国土交通省我が国建設企業の海外PPP事業への参画のための戦略検討会議委員などを歴任。
ベーカー&マッケンジー法律事務所

ベーカー&マッケンジー法律事務所の再生可能エネルギーグループ所属。太陽光発電・陸上・洋上風力発電・地熱発電などの、再生可能エネルギー関連に多数の実績がある。現在は、蓄電池やコーポレートPPAの、法的実務案件を多く受け持っている。内閣府PFI推進委員会専門委員、国土交通省空港運営のあり方に関する検討会委員、国土交通省我が国建設企業の海外PPP事業への参画のための戦略検討会議委員などを歴任。
脱炭素社会への動きが世界的に進むなか、日本政府が掲げる“2050年カーボンニュートラル”実現へ向け、太陽光発電設備を導入する企業が増えています。その一方で、知識不足や安易な導入による火災事故の発生や設置場所・環境をめぐる地域住民との対立など、トラブルが発生するケースも出てきています。
太陽光発電設備導入の際に注意すべきリスクや知っておきたい法規制などについて、多種多様な再生可能エネルギープロジェクトを支援するベーカー&マッケンジー法律事務所の江口直明弁護士に聞きました。

太陽光発電設備で事故が起きた場合、所有者には「工作物責任」が問われます。工作物責任とは、土地の工作物(建物・擁壁 ・道路など)の設置や保存に欠陥があることで他人に損害を生じさせた場合、その工作物の占有者・所有者が負う損害賠償責任です(民法717条)※1。
「大変厳しい責任で、免れることはまずできません。太陽光発電設備を自社所有しないコーポレートPPA(電力購入契約)モデルであっても占有者と認定されれば責任は問われますので、そもそも事故が起きないよう、十分に注意する必要があります。所有者が責任を取るとPPAの契約で定めていても、PPAサービス事業者の対応能力によっては、占有者に責任追及の矛先が向くかもしれません。」
※1 出典・参照元:e-Gov法令検索「民法」第七百十七条
屋根への太陽光パネル設置にあたっては、太陽光パネルを支えるための最低限の基準として、10kg/㎡以上の耐荷重が必要とされていますが、風荷重にも注意が必要です。風荷重については、設置の方法にもよりますが、2017年3月のJIS C 8955の改訂で、旧JIS規定の約2倍の風荷重への考慮が設計時に求められています※2。
「太陽光パネルが風で飛ばされる事故は結構あります。最新の基準をしっかり守って設計・施工していただきたい。近年は太陽光パネルの軽量化も進んでおり、新しい設備や施工技術を選択肢に入れていくことも必要かと思います。」
※2 出典・参照元:公益社団法人土木学会「JISアレイ架台基礎への影響比較」
慣れない事業者の施工ミスで短絡による火災が生じることもあります。屋根からの火災の場合、延焼して建物全体に被害が及ぶため、注意が必要です。
「不慣れなEPC事業者※3もいるため、しっかりと実績のあるEPC事業者を選ぶことが、一つのリスク回避の方法となるかと思います。」
※3 E=設計(Engineering)、P=調達(Procurement)、C=建設(Construction)を一括して行っている事業者のこと
「太陽光発電設備を設置する場合は、まず、その土地自体に問題がないかどうかを徹底的に調査することが、始めの一歩となります。」

その上で、以下のポイントを押さえておきましょう。
トラブル事例として、太陽光パネルの反射光が隣の家に入るといったケースがあります。また、太陽光発電設備に付随するインバータやパワーコンディショナー※4の騒音が原因で問題となる事例も多いです。
※4 インバータとパワーコンディショナーはどちらも太陽光による直流電力を交流電力に変換する装置
こうしたトラブルの場合、裁判所では「受忍限度」の考え方を用います。受忍限度とは、社会共同生活のなかで、騒音や振動などに対し“社会通念上我慢できる”とされる範囲。つまり、音や振動が発生することが全て問題とされるのではなく、それらが受忍限度を超えているかどうかが問題となります。
「太陽光発電設備の設置側が、騒音防止に塀を作ったり、住宅から遠くの土地を選んだりするなど、できる限りの対策を打っておくことは重要です。万一の際に、開発側がいかに努力をしたかが、判断基準の一つとなるからです。」
脱炭素の推進が目的であっても、地域に受け入れられなければ豊かな未来のための投資とは言えません。
「発電事業者には地域住民の合意までは必要ありませんが、事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めることが必要です。国が事業計画策定ガイドラインや説明会および事前周知措置実施ガイドライン※5を作成していることから国として地域住民や自然との共生を重視していることが分かります。需要家が独自に設置したり、オンサイトPPAやオフサイトPPAなどのサービスを導入したりする際も留意が必要です。」
※5 出典・参照元:経済産業省資源エネルギー庁「法令集・契約関係」

第三者所有モデルともいわれるコーポレートPPAでは、基本的にPPAサービス事業者が設備全般の運用・管理を行います。この場合、考慮すべきは、PPAサービス事業者の信用リスクです。
「契約内容、特に事故が起こった場合の補償要件はきめ細かく確認する必要があります。対応にはPPAサービス事業者の体力が相応に必要になる場合もあり、万が一の場合に契約内容通りの対応ができる事業者かどうかの見極めも大事です。」
インターネットなどの情報だけで、優良なPPAサービス事業者を見分けることは難しいです。実際にどれだけ案件をこなしてきたか、過去の実績が一つの判断要因となります。また、専門業者やコンサルタント、EPC事業者などから情報を集めることも重要です。
「提案書を見て、専門的な内容が間違っていないか、実際にはあり得ない見積りを出していないか、良すぎる発電出力を試算していないかなどをチェック。インターネットで過去に事故を起こしていないかといった情報を検索することもおすすめします。説明内容がコロコロ変わるような事業者は要注意。自分の売りたいものではなく、顧客の欲しいものを提供しているかどうかの見極めが大事です。また、複数事業者の見積りを取り、比較検討してみるのも良いでしょう。」
再生可能エネルギーへの転換はグローバルで大きなうねりとなっており、日本国内において各企業も積極的な再エネ導入が迫られています。そこで、現在、再エネ導入の大きなけん引役となっているのが、太陽光発電のコーポレートPPAです。コーポレートPPAの普及に伴い、PPAサービス事業者(以下、PPA事業者)が急増し、さまざまなパターンのモデルが誕生し、需要家として事業者選定における課題に直面するようになりました。本稿では、PPA事業者であるSMFLみらいパートナーズ株式会社のお二人に、太陽光発電のコーポレートPPA採用企業が直面しやすい4つの課題と、それらを乗り越えるための実践的な解決策をお聞きました。効果的にコーポレートPPAを活用するための道筋を確認してみましょう。
関連記事

ゲリラ豪雨や台風の大型化など、地球温暖化による気候変動の影響が身近なものとなりつつあります。
「脱炭素社会の実現に、再エネは非常に重要な役割を果たします。2050年、2100年の世界が、人の住めない世界とならないよう、日々の小さな積み重ねで、追加性のある再エネ、太陽光発電の導入を進めていっていただければと思います。」
(内容、肩書は2025年9月時点)
文・編集:株式会社宣伝会議「環境ビジネス」編集部
※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。
※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。
※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。
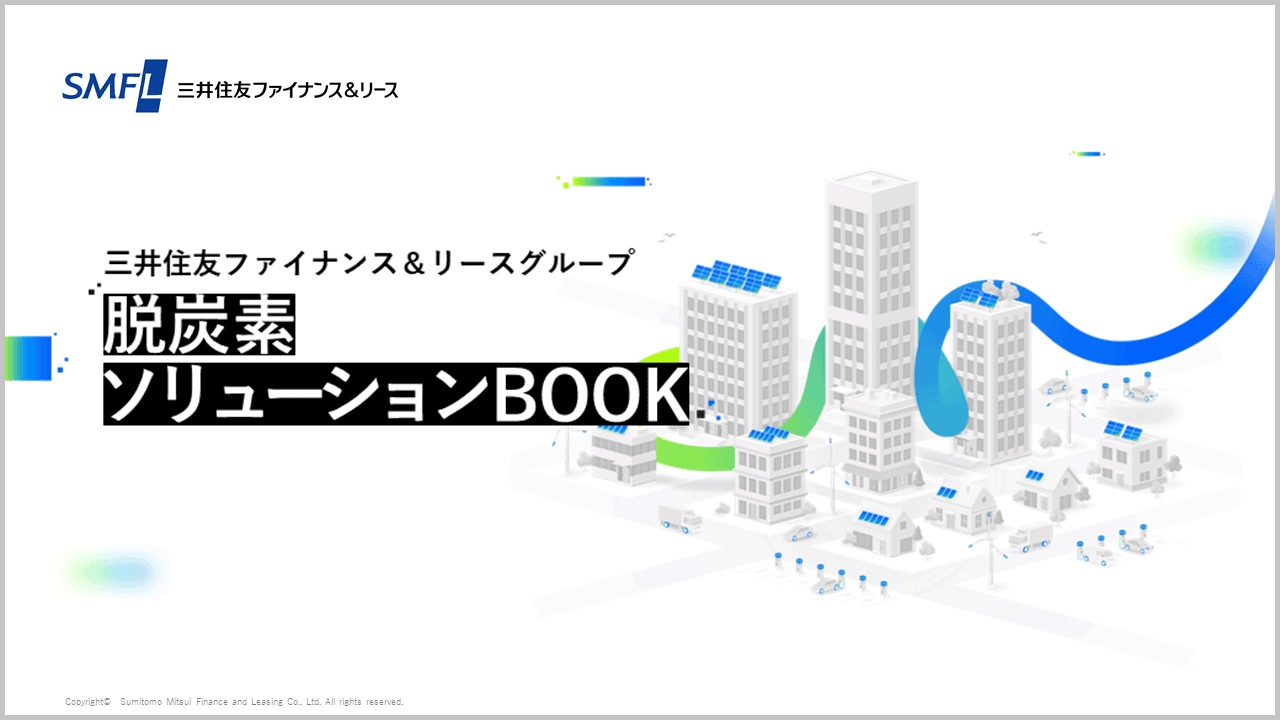
三井住友ファイナンス&リースグループの脱炭素ソリューションを分かりやすく紹介した資料をダウンロードいただけます。
脱炭素実現に向けて、自社に合う具体的なソリューションを探したい方におすすめです。
【個人情報の取り扱いについて】
送信いただいた内容は、三井住友ファイナンス&リースグループ各社にてお問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、商品・サービス情報のお知らせに活用させていただきます。お客さまの同意なしに、回答情報を第三者に提供することはございません。