SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部
村上貴彦(むらかみ・たかひこ)

SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部

SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部
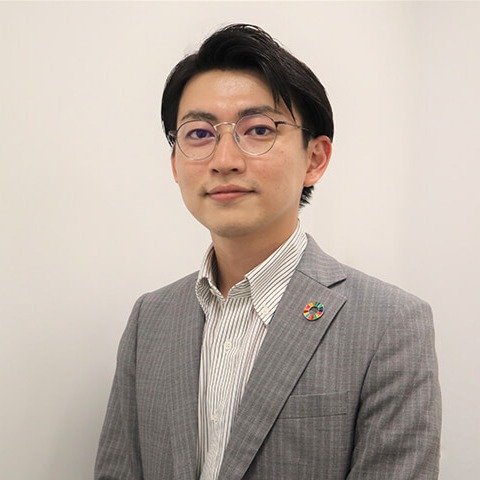
日本では、2020年10月26日、当時の菅総理の所信表明演説において「わが国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」との宣言がなされ※1、これを受けて多くの企業が脱炭素への取り組みを始めています。しかし、取り組みの適切な進め方が分からない、プロジェクトを始めたものの具体的な成果が見えない、などのさまざまな課題に直面し、行き詰まってしまうケースもあるようです。
脱炭素の取り組みが行き詰まってしまうことにはどのような要因があり、どのように解決していけば良いのでしょうか。企業が陥りやすい失敗例とその回避策について、SMFLみらいパートナーズ株式会社の村上貴彦さん、髙橋健太さんに伺いました。
出典・参照元:
※1 環境省 脱炭素地域づくり支援サイト「地域脱炭素とは」
経済産業省資源エネルギー庁「 令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)第1部 エネルギーをめぐる状況と主な対策 第2章 2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と取組 はじめに」

――脱炭素に取り組み始めたものの、データの見える化だけで終わってしまうケースがあるようです。なぜこのようなことが起きるのか、詳しく教えてください。
髙橋健太さん(以下、髙橋):まず、脱炭素推進の最初のステップは、自社の現状を把握すること(見える化)です。現状把握の方法としては、請求書データなどを活用し、自社のエネルギー使用量を認識し、CO2排出量に換算する管理ツールを用いて把握する方法や、工場設備ごとに計測機器を設置し、トラッキングする方法があります。
問題は、これらの見える化を実施した後です。計測データはあってもそのデータを分析するノウハウやスキルがないことや、ノウハウはあっても人手が足りずに手が回らないことなど、うまく活用できていないケースがよくあります。
村上貴彦さん(以下、村上):自社で手が回らないのであれば外部のパートナー企業に依頼する手段もありますが、そもそもそういったパートナーの存在を知らない、というケースも多いです。
――データを見える化して改善策を立案するために、最初のステップとしてはどのような取り組みが必要ですか。
髙橋:まずは脱炭素に取り組む目的を明確にすることが重要です。環境保護、省エネ法※2の事業者クラス分け評価※3の維持、親会社の指示など企業によって脱炭素に取り組む理由はさまざまでしょう。目的を明確にすれば、「何年までにCO2排出量を〇%削減する」などの目標を立てやすくなり、見える化したデータに基づいて具体的な対策を検討しやすくなります。
※2 正式名称はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律。年間に原油換算で1,500kl以上のエネルギーを使用する事業者を対象に、エネルギー使用状況などの報告や、省エネ・非化石エネルギーへの切り替えに向けた取り組みや計画の策定を求めている。
※3 エネルギー使用量が一定以上の事業者を対象に、省エネルギーの取り組み状況を評価し、S・A・B・Cの4段階に分類する制度。
――そもそも「脱炭素に取り組む目的が明確になっていない」企業が多いのでしょうか。
村上:脱炭素に取り組む目的が明確になっていない企業は多いと考えています。「省エネの第一歩は見える化から」と一般的にいわれているために、とりあえずエネルギー計測システムを導入して見える化しただけで終わってしまっているケースがあります。別の例だと「脱炭素のためには太陽光発電設備の導入が不可欠だから」と、そこだけをピンポイントで実行してしまうようなケースもあります。また、同じ企業の中でも部門ごとに目的がバラバラのままで進んでいるケースも散見されます。
「まずは全体を把握し、脱炭素に向けて自社がやるべきことの優先順位をつけて計画を立て、足並みをそろえる」ということが、なかなかできていません。
――そういった企業に対して、どのようなサポートをしていますか。
髙橋:SMFLみらいパートナーズ株式会社(以下、当社)では、お客さまに確認しながら脱炭素の実施目的を整理するところからサポートしています。
サポートの流れは、目的を整理した後、具体的な対策の立案に進みます。お客さまのエネルギー使用状況や設備保有状況などの現状を網羅的に把握するため、問診を行った上で、パートナー企業とともに対象となる工場へ赴いて、ヒアリングを経て、具体的な実施計画を提案するという流れです。データの見える化については、エネルギー見える化サービスといったサービスを提供しております。計測システムの導入とそのシステムから取得したデータの分析診断を行い、改善策の立案やその改善に伴う削減効果の試算を実施します。
村上:やはり実際に現地へ行くことが大切だと感じています。どんな設備を使っているかは問診票で把握できますが、その設備の使われ方や運用方法は実際に見てみないと分かりません。また、実際に担当者の方にヒアリングすることでより詳しい実態を把握できるので、改善案を立案しやすくなります。
――企業によって、工場の規模や数もさまざまかと思います。どこまでをデータ計測・改善の対象とするかなどが難しいように思いますが、どのように対応していますか。
村上:「脱炭素に取り組む目的に照らし合わせた際に、どこに機器を設置して計測するのが最も効果的か」といったことを、パートナー企業のノウハウも活用しながら提案しています。例えば、エネルギー使用量が多い工程や長時間稼働する生産ラインでは、改善余地が大きい可能性があるため、このような工程にフォーカスして診断を行うケースや、逆にある程度自動化されている工程では改善余地が少ない可能性があるため、優先度を下げるといったケースがございます。より大きな効果が得られるような提案を実施しております。
――脱炭素に取り組んでいる企業に対し、見える化の次の段階に進むためにはどんなサポートができますか。
髙橋:当社では「自社で実施できることはやり切った」というお客さまに対しても、さらなる提案を実施したいと考えています。
エネルギー見える化サービスによって、自社だけでは見過ごしていた課題を見つけられる可能性があります。例えばエネルギーの無駄が見つけられていないといった課題や、生産ラインの待機時間に基づく非効率性といった課題です。生産ラインの稼働状況とエネルギーの使用状況のデータを比較して、増減が比例しないといったエラー状況の見える化を通して、設備投資を伴う改善案だけではなく、新たな運用改善案も立案することで、より効果的な脱炭素の推進が可能だと考えています。

――脱炭素を推進するにあたって、なぜ部門間で認識の不一致が起こるのでしょうか。
髙橋:大きな要因は、部門間で目標に違いがあることです。同じ企業内でも、CO2排出削減に注力する部署もあれば、損益に注力する部署もあります。脱炭素の取り組みにかかるコストについてどのようにバランスを取るべきか、共通認識を持ちにくい、といった声をよく伺います。
――経営層と現場では、どちらが脱炭素に対しての意識が高いのでしょうか。
村上:どちらのケースもあります。例えば現場の方が経営層よりも意識が高い場合だと「省エネによってエネルギーコストが削減できる」というメリットから現場が中心になって脱炭素を積極的に推進しているケースがあります。また、省エネ法に対応している工場は経済産業省に定期報告書や中長期計画書を提出する必要があるので、省エネに取り組むことが「当たり前のもの」として浸透している現場も多くあります。
ほかには、老朽化した設備について「急に壊れて使えなくなると困る。省エネにもつながるので、壊れる前に高効率な機器に代えたい」という声が現場から上がることもあります。
髙橋:ただ全体で見ると、脱炭素の推進はステークホルダーからの評価や株価への影響を懸念する経営層からの関心が高く、トップダウンで推進されている印象です。また、現在では大企業や上場企業の方が、経営層の脱炭素への意識が高いことが多いと感じます。
――トップダウンの場合、現場の従業員意識の浸透が重要になると思います。企業全体で意識を共有するための鍵は、どういった点にあるのでしょうか。
村上:経営層が経営方針として「脱炭素に取り組む」姿勢を強く打ち出すのが一番早いと思います。トップダウンでいかないと、取り組みとしての優先順位が下がるなどして有耶無耶に終わってしまいがちです。
トップから強いメッセージとして、国としての課題であるCO2排出削減と、その先にあるカーボンニュートラル※4の実現に向けた取り組みの重要性を打ち出すことで、従業員一人ひとりが認識しやすくなると考えています。
当社がこれまでに提案を実施したケースでは、当初は投資回収期間が重視されたケースもありました。そのお客さまの設備は老朽化による更新が必要だったため、事業継続リスクといった観点に加え、設備更新によって大きな省エネ効果が見込まれる点も併せて社内説明いただき、国の方針にも合致することから、賛同していただけました。
当社は「コスト面だけではなく、エネルギー削減効果やCO2削減効果も踏まえて投資計画を考えていただけませんか?」と担当者さまにお伝えしています。
インターナルカーボンプライシング※5を導入される企業も増えつつあるように、CO2削減効果も踏まえて投資計画を考えるのが重要との認識も広まってきています。
※4 二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減しつつ、植林や吸収技術で排出分を相殺し、実質的に排出量をゼロにする考え方。日本政府は2050年までの実現を目指している。
※5 企業や組織が内部で使用する、二酸化炭素の排出量に価格を付ける仕組み。この仕組みによって、排出削減のインセンティブを高め、カーボンニュートラルや持続可能な経営への取り組みの促進が期待されている。
――脱炭素への意識の不一致を解消するためには、具体的にどのようなアプローチが考えられますか。
髙橋:例えば当社のエネルギー診断サービスを利用いただいたお客さまに、「診断報告会」を開催する、といった方法は効果的と考えています。経営層から現場まで、幅広い方に向けてCO2削減効果を報告するとともに、カーボンニュートラル推進にあたって検討できる事例を紹介することで共通認識を持っていただく機会になるからです。
こういった情報共有により、異なる部門の方々が共通認識を持ち、意識の不一致を解消することにつながると考えています。実際、削減効果を数値で見たことにより取り組みへの意識が高まったという反応もありました。
村上:「本社からいろいろ言っても現場が従ってくれない」といった話や、逆に「省エネの推進担当者が経営層に提案をしても動いてくれない」といった話はよく耳にします。こうしたケースでは、われわれのような第三者が間に入って「このような改善余地がありますよ」と提案すると、素直に耳を傾けてくださることがあります。

――まず、脱炭素の推進において設備投資が重要な理由を教えてください。
村上:脱炭素の推進にあたっては、再生可能エネルギー設備や省エネ設備の導入が必要です。
新規設備の導入や、既存設備を高効率なものへ更新するだけでなく、今ある設備に自動制御やインバーター制御などを加えることによって自動的に効率的な運転ができるように改善する方法もあります。
また、そもそもどんな設備であっても長年使っていれば経年劣化していくので、新品に変えることで今よりも性能が上がります。その際、単に後継機種に更新するのではなく、省エネ性能の高いハイグレードな設備に更新することで、より高いCO2削減効果を得ることができます。十分な再エネ導入量や省エネ効果を得るためには、大きな投資をする方が効果的だといえるでしょう。
髙橋:当社の場合は、先ほどお話した問診票に記入されたお客さまの情報を基に、具体的なCO2削減効果をシミュレーションしています。
――設備投資において、特にどういった部分に大きなコストがかかるのでしょうか。また企業規模によって、資金調達の難易度は変わりますか。
髙橋:再生可能エネルギー設備の初期導入費用や、既存の施設や設備が老朽化している場合の更新コストなどが代表的なものです。高額なコスト負担になることから、特に中小企業では設備投資費用を確保しにくい傾向にあります。
――設備投資費用の確保が難しい企業が脱炭素を進めるためには、どうすれば良いでしょうか。
髙橋:国や自治体が出している補助金を活用する方法があります。当社でも幅広い種類の補助金サポートを行っていますが、経済産業省のいわゆる「省エネ補助金(省エネルギー投資促進に向けた支援補助金)」などが選択肢の一つです。
――「補助金を使いたいが、自社に適したものを選ぶのが難しい」といった課題もあるかと思います。補助金に関する知識が不足している企業に対しては、どのような支援が考えられますか。
髙橋:当社の場合は「こんな投資をしたいが、使える補助金はあるか」というご相談を受けたら、まずはお客さまの現状をヒアリングし、国や自治体の補助金の中から最適なものを提案します。
そして補助金の申請は、場合によって50種類以上もの書類を作成しないといけません。さらには申請後も不備指摘や質疑の対応や、採択されてからもさまざまな報告書を作成する必要があります。当社では採択後の対応についても、一気通貫でサポートしています。
――補助金のサポートを受けるにあたって、企業側で検討や準備をしておくべきことを教えてください。
髙橋:当社のようなパートナー企業に相談いただく場合は「いつ、何の設備を、どれぐらいの金額で設備投資するのか」という、おおよそのスケジュール感と設備投資にかけたい金額感を決めておいていただくのがスムーズだと思います。
村上:国の補助金は申請できる期間が決まっています。例えば、先ほど例に挙げた経産省の省エネ補助金のⅠ型では「原油換算で〇〇kl削減してください」などの要件があります。要件を達成するためには1億円の設備投資では省エネ効果が足りず、場合によっては10億円ほど必要になることもあります。
どのような補助金を提案するかによって要件や設備投資の金額が変わりますので、最適な補助金を提案するためにも、スケジュール感と金額感はあらかじめ検討しておいていただけたらと思います。
地球温暖化や気候変動の進行を抑える取り組みが各国で進められている中、企業活動にもGHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)削減が求められています。今や、企業がGHG削減を「当然のもの」として取り組まなければなりませんが、施策を計画、実行するフェーズにおいて、企業はどのような課題に直面するのでしょうか。また、GHG削減にはどのような解決策があるのでしょうか。企業のGHG削減を支援するSMFLみらいパートナーズ株式会社のお二人に詳しく伺いました。
関連記事

(内容、肩書は2025年3月時点)
取材・構成:吉玉サキ/編集:はてな編集部
※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。
※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。
※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。

最新の補助金/税制/脱炭素ソリューションを分かりやすく紹介した資料をダウンロードいただけます。
【個人情報の取り扱いについて】
送信いただいた内容は、三井住友ファイナンス&リースグループ各社にてお問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、商品・サービス情報のお知らせに活用させていただきます。お客さまの同意なしに、回答情報を第三者に提供することはございません。