SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部
村上貴彦(むらかみ・たかひこ)

SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部

SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部

再生可能エネルギーへの転換はグローバルで大きなうねりとなっており、日本国内において各企業も積極的な再エネ導入が迫られています。
そこで、現在、再エネ導入の大きなけん引役となっているのが、太陽光発電のコーポレートPPA※1です。コーポレートPPAの普及に伴い、PPAサービス事業者(以下、PPA事業者)が急増し、さまざまなパターンのモデルが誕生し、需要家として事業者選定における課題に直面するようになりました。
本稿では、PPA事業者であるSMFLみらいパートナーズ株式会社のお二人に、太陽光発電のコーポレートPPA採用企業が直面しやすい4つの課題と、それらを乗り越えるための実践的な解決策をお聞きました。効果的にコーポレートPPAを活用するための道筋を確認してみましょう。
※1 PPAは「Power Purchase Agreement(電力購入契約)」の略で、PPA事業者が提供した太陽光発電電力に対して、需要家が使用量に応じて料金を支払う契約形態のこと。PPA事業者が、自らの費用で太陽光発電設備を設置し、契約期間中において運用・維持管理を行う

──PPA事業者のサービス内容に違いが出やすい部分はどこでしょうか。
永島愛望さん(以下、永島):違いが現れやすいのは太陽光発電設備導入後の日常管理や保守などの対応です。具体的には、日常的な発電量のモニタリングや不具合発生時の対応方法、定期点検の項目などが挙げられます。
そのほかにも、契約期間中のPPA単価の見直しなど需要家としてのペナルティ条件、自然災害発生時の対応範囲、中途解約時の条件、補助金活用サポートの実績といったさまざまな違いがあることから、こうしたポイントをPPA事業者ごとに横並びで比較検討することが重要です。
──信頼できるPPA事業者かどうかを見極める上で、特に注目すべきポイントはありますか。
永島:まずは、リスクも含めて、各種条件が提案時にきちんと説明されているかどうかがポイントです。契約期間中の運用維持管理においてPPAサービスに含まれていない対応事項がある場合、別途対応可能な業者に依頼が必要となり、別途費用負担が発生します。
また、コーポレートPPAの実績も安心して任せることができるか判断する一つの材料になるかと思います。自社が導入を検討している建屋と同程度の規模、条件での実績があるかを、PPA事業者に確認することが大切です。
例えば、製造工場や倉庫、物流センターなど大規模な建屋への設置を考えている場合、発電規模がMW(メガワット。1MW=1,000kW)単位になることが予想されます。コンビニエンスストアやスーパーなど100kW単位の比較的小規模の案件を取り扱うPPA事業者では、ミスマッチが発生するおそれがあります。
さらに、PPA事業者だけでなく、設計・施工を行うEPC(Engineering:設計、Procurement:調達、Construction:建設工事)事業者の、全量売電型ではなく、自家消費型の太陽光発電設備工事の実績もしっかりと確認してください。
当社を例にとると、コーポレートPPAの黎明期である2019年4月からPPAサービスの営業を開始し、国内の大規模製造工場を中心に契約実績を延ばしており、現在では累計契約実績100MWを超えています。提案を受ける中で、具体的な実績をPPA事業者に質問し、判断材料の一つとして活用するのがおすすめです。

──コーポレートPPAの契約期間は一般的に20年です。なぜ長期契約が必要なのでしょうか。
村上貴彦さん(以下、村上):太陽光パネルは長寿命であり、長期間使用する発電設備のため、運用期間の実態に合わせた契約期間が設定されています。
長期契約により、PPA事業者は設備の初期投資や期中経費を長期間かけて回収できるため、PPA単価が抑制できます。商用電力の購入単価より安価になるケースも多く、需要家がコーポレートPPAを採用しやすくなります。
──単価を低く抑えられること以外にも、需要家が長期契約を結ぶメリットはありますか。
村上:そもそも脱炭素実現までのプロセス自体が長期的な取り組みです。2030年の温室効果ガスを46%削減する中間目標や、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギーの長期安定確保は、企業にとって大きなメリットです。
各企業が本来必要な再生可能エネルギーである太陽光発電を、保有・運用することなく調達できることは、各企業の社員が本業に集中でき、手間や運用リスクの負担が軽減される面からも大きなメリット言えるでしょう。
──一方で、長期契約のリスクとしてはどのようなものが考えられますか。
永島:リスクとしては、中途解約が原則不可ということが挙げられます。例えば、契約期間中に、建屋の改修や移転など、コーポレートPPAを採用する需要家の都合で中途解約することになった場合、中途解約金の支払いが発生します。
ほかに、長期契約で懸念されることがPPA事業者の倒産や事業撤退のリスクです。比較検討する際は、その業者に20年後も事業を継続できるだけの安定性や信頼性があるかどうかをしっかりと見極めることが重要です。
──こうしたリスクに対して、どのような対応が考えられるでしょうか。
永島:まず中途解約せざるを得ない状況にならないよう、太陽光パネルの設置に適した建物かどうか、最低でも20年間は発電を続けられる建屋かどうかを慎重に検討されることをおすすめします。
実績が豊富でノウハウを有するPPA事業者からのアドバイスも受けながら、建て替え計画がないか、電力使用量に大きな変化が発生しないかなど、社内の関係部署とも協議の上、検討を進めていくのが良いでしょう。
脱炭素社会の実現のため、企業にも対応が求められる中、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー(再エネ)の導入を検討する企業が増えています。脱炭素を進める上で、実効性が高い選択肢として特に注目されているのが、コーポレートPPA方式での太陽光発電の導入です。
関連記事


──契約期間満了後の対応についても、需要家が検討すべきポイントだと思います。契約期間が終わった後、太陽光発電設備はどうなるのでしょうか。
永島:一般的に、三つのパターンがあります。
一つ目は、契約終了後、PPA事業者から需要家に太陽光発電設備が譲渡され、自社設備として所有するパターン。二つ目は、契約終了後、太陽光発電設備を撤去するパターン。そして三つ目が、太陽光発電設備をメンテナンスの上、再契約・PPAサービスを継続するパターンです。
──一つ目の太陽光発電設備が譲渡される場合ですが、需要家はどのような対応が必要になりますか。
村上:太陽光発電設備の所有権がPPA事業者から需要家へと移ることで、それまで負担のなかった日常管理や定期点検、不具合時の修理・交換対応、自然災害による設備破損時の保険会社対応など、運用主体者として必要な業務を全て行うことになります。
契約終了後、それまでPPA事業者に支払っていたサービス料金は不要になりますが、自社で発電設備の運用維持管理のためのコストやマンパワーが必要となる点は考慮しておくべきです。
──引き続き再生可能エネルギーの活用が必要だが、太陽光発電設備の自社運用が困難な場合、三つ目の再契約によるPPAサービスを継続する方法があるのですね。
永島:そうですね。この場合、発電を継続するため需要家はこれまで通り、手間なく太陽光で発電した再生可能エネルギーを購入・使用し続けることができます。
当社では、どんな方法がその需要家に適しているのか、個々のケースに寄り添って最適な方法をご提案しています。

──提案を受けたコーポレートPPAのリスクはどのタイミングで把握できますか。
永島:特に気を付けたいのは、契約内容のドラフトをすり合わせる段階です。この段階で、提案書には記載がなかった情報が初めて出てきて、需要家が戸惑うケースも少なくありません。
そして、残念ながらそうした情報の中には、需要家にとって不利な内容が含まれていることもあります。
──需要家にとって「不利な内容」とは、どのようなものでしょうか。
永島:太陽光発電設備の不具合や自然災害による設備損壊時、太陽光電力使用量低下時など、需要家にて費用やリスクを負担しなければならない場合があります。
また、中途解約ができないことや価格変動の可能性について説明が不十分な場合も注意が必要かもしれません。
村上:PPAは「Power Purchase Agreement」の略称で「電力購入契約」という意味であるものの、電力会社と交わす通常の契約とは全く異なるという意識を持つことも重要です。
通常の電力契約は1年が基本ですが、コーポレートPPAは先ほど説明したように20年にも及ぶ長期契約。解約金も発生するため、一度契約してしまうと別の会社に切り替えることは、基本的には難しくなります。
また、課題1で述べたように、さまざまなPPA事業者が混在し、契約書の内容に大きな差があるのも、通常の電力契約と異なる点です。PPA単価だけに注目せず、内容や条件をしっかりと確認してから契約を行うと良いでしょう。
PPA事業者の提案をただ聞くばかりではなく、少しでも不安や疑問を感じたら、詳細に確認し、場合によっては契約前に引き返す判断をすることも必要だと思います。
脱炭素社会への動きが世界的に進むなか、日本政府が掲げる“2050年カーボンニュートラル”実現へ向け、太陽光発電設備を導入する企業が増えています。その一方で、知識不足や安易な導入による火災事故の発生や設置場所・環境をめぐる地域住民との対立など、トラブルが発生するケースも出てきています。
関連記事

──最後に、コーポレートPPAの採用を検討している需要家に対して伝えたいことはありますか。
永島:初めてコーポレートPPAを採用する需要家にとっては、何をどのように検討すべきなのか不明瞭な点が多いでしょう。そのようなときに比較すべきポイントを詳細に説明し、安心して採用に踏み切れるようサポートしてくれるPPA事業者を探すのも一つの手段です。
村上:当社も、企業の脱炭素化を支援する長期的なパートナーとして「20年先まで付き合いたい」と思っていただけるよう、お客さまに寄り添って、信頼性の高いサービスを提供し続けたいと考えています。
(内容、肩書は2025年3月時点)
文:白石沙桐/編集:はてな編集部/編集協力:株式会社エクスライト
※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。
※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。
※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。
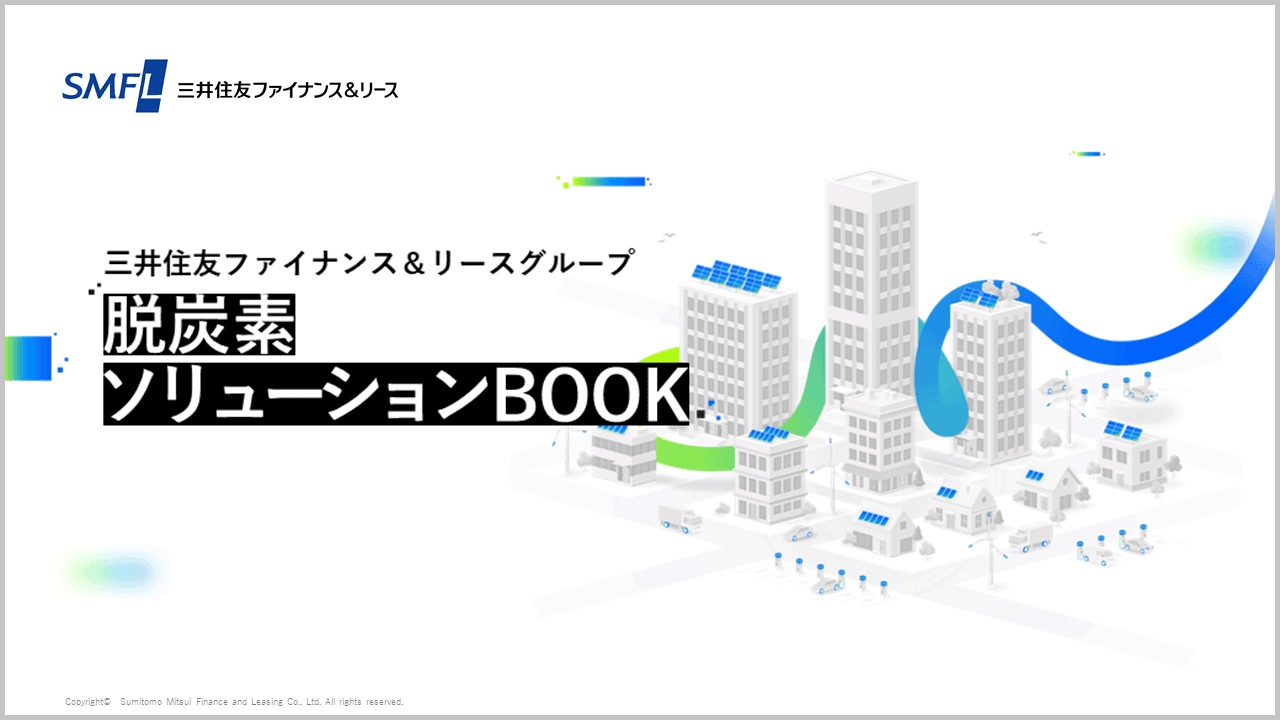
三井住友ファイナンス&リースグループの脱炭素ソリューションを分かりやすく紹介した資料をダウンロードいただけます。
脱炭素実現に向けて、自社に合う具体的なソリューションを探したい方におすすめです。
【個人情報の取り扱いについて】
送信いただいた内容は、三井住友ファイナンス&リースグループ各社にてお問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、商品・サービス情報のお知らせに活用させていただきます。お客さまの同意なしに、回答情報を第三者に提供することはございません。