信州ボルタ株式会社科学技術顧問
是津信行(ぜっつ・のぶゆき)

大学で蓄電池およびその材料技術を研究。現在は水系電池や全固体電池の開発に取り組んでおり、これをスマートフォンや未来の電気自動車などに搭載することを目指している。
信州ボルタ株式会社科学技術顧問

大学で蓄電池およびその材料技術を研究。現在は水系電池や全固体電池の開発に取り組んでおり、これをスマートフォンや未来の電気自動車などに搭載することを目指している。
近年、企業による太陽光発電の導入が進んでいますが、これまで以上に太陽光発電を活用する取り組みとして蓄電池を組み合わせた電力貯蔵システムの導入が注目されています。
本記事では、蓄電池の歴史から、電力貯蔵システムがもたらす効果、導入・運用時のポイント、蓄電技術の展望まで、リチウムイオン蓄電池などの研究に取り組む是津信行さんに取材しました。
蓄電池がどのように普及し、進化してきたのかについて解説します。
電池は大きく二つの種類に分けられます。

身近な例としては携帯電話などの家電に搭載される蓄電池があります。そのほとんどが「リチウムイオン電池」と呼ばれているもので、1970年代に開発されました。
リチウムイオン電池の登場以前は、「ニッケル水素電池」や「ニッケルカドミウム電池」が主流でした。リチウムイオン電池はそれらと比べ、長寿命で、エネルギー密度※1が高く、短時間で大きなエネルギーを取り出せるという特徴があり、急速に普及しました。
※1 電池が重量や体積当たりでどれだけ多くのエネルギーを蓄えられるかを示す指標
当初、リチウムイオン電池は蓄電池として利用できず、使い捨てカメラのストロボなどの用途で一次電池として実用化されました。その後の技術革新により蓄電池としての利用が可能となり、1990年代には携帯電話や電動工具用の小型バッテリーとして活用されるようになりました。
2000年頃には、日本国内でもEV(電気自動車)のモーターを駆動させる車載用バッテリーとして蓄電池が注目され始めました。ただし、リチウムイオン電池は外部からの衝撃による発火のリスクが懸念されていました。そのため、当初のEVには、不燃性で電池が暴走しても発火しない特性を持つニッケル水素電池が採用されていました。
その後、リチウムイオン電池の安全対策技術が進展したことで、発火の懸念は低減されました。リチウムイオン電池はニッケル水素電池よりも大容量で、EVの走行距離を伸ばせる利点があるため、車載用バッテリーに使われるケースが増えました。
| 時期 | 電池の種類 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1970年代 | 一次電池 | カメラのフラッシュなど | 当初はリチウムイオン電池を蓄電池として活用する技術がなかった |
| 1990年代 | 二次電池(蓄電池) | 携帯電話・電動工具など | 技術革新により、蓄電池としての利用が可能になった |
| 2000年代 | 二次電池(蓄電池) | EV(電気自動車) | EVの普及に伴い、従来の電池よりも高電圧でエネルギー密度の高いリチウムイオン電池が普及した リチウムイオン電池普及の経緯 |

リチウムイオン電池の普及と同時に、太陽光発電設備などで発電した電気をためる定置用と呼ばれる蓄電池の開発も進んでいきます。
定置用蓄電池としては、リチウムイオン電池のほかにも以下のような種類があります。
リチウムイオン電池は常温で作動し、高出力の充放電が可能です。また、エネルギー設備や航空宇宙分野の設備など多用途に使えることから、現在は世界中のメーカーが開発競争を繰り広げています。大量生産により近年では価格が下がったため定置用としても評価されています。
エネルギー密度の高さと低価格という優位性から、リチウムイオン電池は蓄電池市場で多くのシェアを獲得し、太陽光発電設備などと組み合わせ、効率的に電気を使用する動きも広がっているのです。
次世代の蓄電池として注目されているのが「全固体電池」です。
全固体電池には、以下のような特徴があります。
特に、充電時間の短さは、全固体電池の大きなメリットの一つです。例えば、リチウムイオン電池を使用したEVは充電に最短でも約30分はかかりますが、全固体電池であれば数分にまで短縮できると期待されています。
とはいえ、全固体電池は研究開発が進んでいるものの、まだ製品化には至っていません。コストはリチウムイオン電池の10倍以上とされており、車載用バッテリーとしての実用化は早くても数年後と見込まれています。
さらに、民生用や定置用の全固体電池の実用化には10年以上を要すると言われており、2035年時点では引き続きリチウムイオン電池が主流であると、是津さんは考えています。

蓄電池の進化に伴い、近年は太陽光発電設備で発電した電気を安定供給するために電力貯蔵システムが活用されています。電力貯蔵システム(ESS:Energy Storage System)とは、太陽光などで発電した電力を一時的に蓄えて必要な時に供給するための、電力の貯蔵と制御を行うシステムの総称です。その主要な構成要素の一つとして蓄電池が組み込まれています。
太陽光発電設備と蓄電池を併用することは、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
太陽光発電は、天候や時間帯、さらに冬季における日照時間などの季節的要因で発電量が変動します。
このような課題を解決するために、発電した電力を一時的に電力貯蔵システムの蓄電池に蓄え、電力が必要な時間帯に供給する仕組みを構築することで、安定的な電力供給が可能となるのです。
企業が地震などの災害に備えるBCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)として電力貯蔵システムを導入すれば、停電時には電力会社からの電力供給の復旧を待たずに太陽光発電設備で発電した電力を利用できます。
いつ発生するか分からない災害に備えるには、電力貯蔵システムの蓄電池を常に満充電の状態に保っておく必要があります。同時に、電圧や電流を一定に保ちながら短時間に大きな電流を流す能力も不可欠です。
安全性を確保しつつ短時間で大電流を流せるのは、現状ではリチウムイオン電池が最適で、太陽光発電設備とリチウムイオン電池の定置用蓄電池が、よく使われる組み合わせであると是津さんは話します。
電力の需要家(企業)が実際に蓄電池を使った電力貯蔵システムを導入する際は、どのような点に留意する必要があるのでしょうか。是津さんは、見落としがちなポイントとして以下の2点を挙げます。
電力貯蔵システムの導入検討時には、設備の寿命についても考慮が必要です。導入後、一定期間が経過すれば設備の更新が必要となり、大きな費用が発生することがあるためです。
太陽光発電設備については、太陽光発電の普及とともに導入コストが大幅に低下しており、更新の負担はそれほど大きくありませんが、太陽光パネルを廃棄することになった際は費用が発生します。50kW以上の産業用太陽光発電設備(野立て)の場合、廃棄コストの相場は「kWあたり約2万円」と言われているため、50kWであれば約100万円 が必要となります。
また蓄電池についても、買い替えや廃棄のコストに留意しておくべきでしょう。近年では、電池のリサイクル技術が進展しており、電池からレアメタルを取り出して再利用する取り組みが始まっているものの、売却額が廃棄額を上回るようになるまでには、まだ時間がかかると考えられています。
このように、電力貯蔵システムを導入する際は、廃棄後の処理まで考慮した計画が求められます。
太陽光などの再生可能エネルギーを導入する本来の目的は、2050年のカーボンニュートラルに向けてCO2(二酸化炭素)をはじめとする温室効果ガスの排出量を削減することです。その目的を達成するためには、効率的に再生可能エネルギーを供給するためのエネルギー管理システム(EMS:Energy Management System)」による最適化が必要になります。
エネルギー管理システムは、一般的な電力貯蔵システムに含まれているもので、太陽光発電設備の発電状況や蓄電池の充電状況をモニタリングし、最終的に工場などで必要とされる電力量を「見える化」できるシステムです。データを分析することでエネルギー消費の効率化が可能になるため、現場の状況に応じてパフォーマンスを向上させることができます。

ここまで企業での蓄電池を使った電力貯蔵システムの運用について見てきましたが、では今後、このシステムはどのような活用方法へと広がりを見せていくのでしょうか。最後に、よりマクロな視点から、先進的な取り組み事例を通じてその可能性を考察します。
電力貯蔵システムは、製造業や都市部の電力供給に限らず、さまざまな産業においても重要な役割を果たします。特に一次産業において、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みが進んでいます。
是津さんは、先進的な活用事例の一つとして「陸上養殖」に注目しています。陸上養殖とは、陸上の人工的な環境下で食用の魚を育てる方法であり、海洋汚染を避けつつ水産資源を守ることから「地球に優しい漁業」として注目されています。
陸上養殖の施設は、山間地に建設されることもあります。山間地のように電力が確保しにくい地域でも、再エネ設備と蓄電池を組み合わせた電力貯蔵システムの活用により、安定した電力供給が可能になります。また使用する電力は再生可能エネルギー由来のため、さらに地球環境に配慮した漁業を実現できるというわけです。
前述したように、山間地は送電線の設置場所が限られ電力供給が不安定になるため、産業用地化が困難であるという課題があります。
日本の国土は、約75%が山間地(丘陸地を含む)です※2。送電線を必要としない電力貯蔵システムを活用することで山間地の産業利用が可能になれば、国土の多くの部分を産業地として活用できるポテンシャルが高まります。実際に、電力貯蔵システムを活用して、山間地での環境計測に必要な電力を供給する事例も生まれています。
※2 出典・参照元:国土地理院「1990年刊行 新版日本国勢地図」
蓄電池を含めた電力貯蔵システムは、再生可能エネルギーのさらなる活用を後押しする可能性が高いと言えます。将来的には全固体電池が実用化され、蓄電池の性能が飛躍的に向上する可能性もあります。
また、AIの活用が進む中で、電力管理もさらなる効率化が進むと期待されます。
今後、企業はこれらの技術動向を注視して積極的に電力貯蔵システムを取り入れ、エネルギー戦略の見直し・強化を継続する必要があるでしょう。
(内容、肩書は2025年5月時点)
文:元田光一/編集:はてな編集部/編集協力:株式会社エクスライト
※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。
※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。
※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。
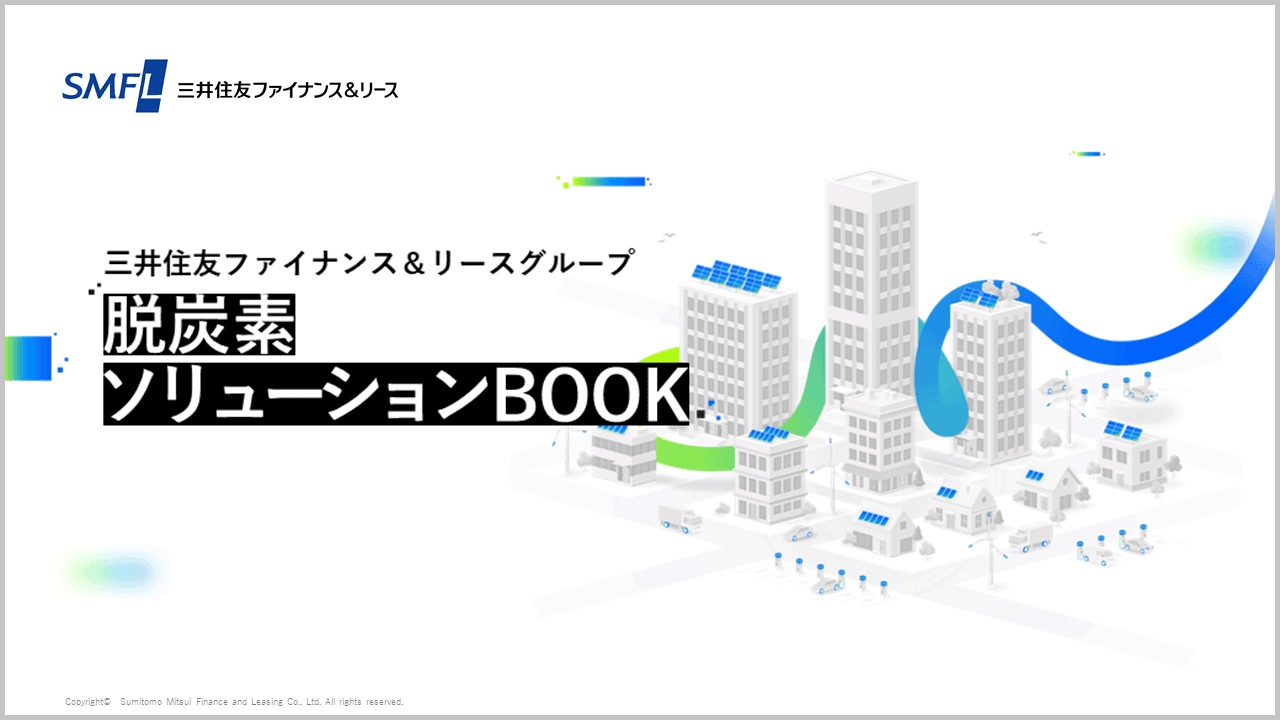
三井住友ファイナンス&リースグループの脱炭素ソリューションを分かりやすく紹介した資料をダウンロードいただけます。
脱炭素実現に向けて、自社に合う具体的なソリューションを探したい方におすすめです。
【個人情報の取り扱いについて】
送信いただいた内容は、三井住友ファイナンス&リースグループ各社にてお問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、商品・サービス情報のお知らせに活用させていただきます。お客さまの同意なしに、回答情報を第三者に提供することはございません。