SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部
村上貴彦(むらかみ・たかひこ)

SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部

SMFLみらいパートナーズ株式会社
エネルギーサービス部

地球温暖化や気候変動の進行を抑える取り組みが各国で進められている中、企業活動にもGHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)削減が求められています。
今や、企業がGHG削減を「当然のもの」として取り組まなければなりませんが、施策を計画、実行するフェーズにおいて、企業はどのような課題に直面するのでしょうか。また、GHG削減にはどのような解決策があるのでしょうか。企業のGHG削減を支援するSMFLみらいパートナーズ株式会社のお二人に詳しく伺いました。

──企業活動にGHG削減が求められている背景について教えてください。
永島愛望さん(以下、永島): 2015年に採択されたパリ協定で、2020年以降の温室効果ガス削減に関する世界的な取り決めが示されました。それを受けて日本は「2030年度までに2013年度比でGHGを46%削減する」「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指す」という目標を掲げています。
現在はこの目標達成に向けて、各企業がGHG削減を推進している状況です。「RE100※1」や「SBT※2」などの国際的な枠組みに多くの企業が参加しています。
※1 企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ
※2 企業が設定する、科学的根拠に基づいたCO2排出量削減目標
出典・参照元:環境省「令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」第3節 炭素中立(ネット・ゼロ)
──企業がGHG削減に取り組むことには、どのような意義やメリットがあるのでしょうか。
永島:地球温暖化進行や気候変動リスクを抑えるGHG削減は、日本政府として取り組むことを決めており、社会の一員である各企業には、積極的にGHG削減に取り組む社会的使命があります。
これまで、GHG削減に取り組むことは、環境に配慮した企業であるというアピールやブランドイメージの醸成効果と捉えられていました。
近年では、消費者や取引先企業からの評価や資金調達、株価への影響など、経営面でもメリットを享受できる可能性があると言われています。
──企業がGHG削減を進める際に、どのような課題に直面するのでしょうか。
永島:企業のGHG削減を推進するサステナビリティ推進担当の方と会話をすると、そもそも自分たちの会社や工場がどれだけCO2を排出しているのかを把握できていない、といった計画を策定する前段階の課題に直面していることが多いです。
また、サステナビリティ推進担当の方の課題感と、経営層や製造現場(工場)の方の課題感に、大きなギャップがあり、企業全体で大きな推進力が得られないというパターンもよく聞きます。
さらに、企業としてGHG削減への意識が高くても、「どんな方法で取り組めばいいのか分からない」という悩みから、「資金をどうやって捻出すればいいのか」といった具体策まで、企業が直面する課題は千差万別です。
村上貴彦さん(以下、村上):以前は、老朽化した機器を最新のものへ更新することで結果的に省エネに繋げる受動的な省エネの取り組みの話を聞くケースがありました。
しかし、現在ではGHG削減の目標値への到達には受動的な省エネだけでは不十分と考えられています。老朽化更新に加えて、廃熱利用などの能動的な省エネを組み合わせた徹底した省エネが必要であり、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入も不可欠です。
GHG削減の取り組みは高度化しているので、複数の手段を効果的に実行しながらGHG削減を推進するためには、総合的なソリューションを持ったパートナー企業の活用も非常に重要だと考えています。
日本では、2020年10月26日、当時の菅総理の所信表明演説において「わが国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」との宣言がなされ※1、これを受けて多くの企業が脱炭素への取り組みを始めています。しかし、取り組みの適切な進め方が分からない、プロジェクトを始めたものの具体的な成果が見えない、などのさまざまな課題に直面し、行き詰まってしまうケースもあるようです。
関連記事


──企業が実際にGHG削減のサポートを受ける場合、どんな課題がありますか。
村上:GHG削減には以下のようなフェーズがあります。
企業が外部の事業者にフェーズや施策ごとのサポートを求めるケースもよくありますが、その場合、やりとりが煩雑になるだけではなく計画と結果がうまく結びつかないおそれもあります。
例えば、現状把握・削減対策立案フェーズは省エネコンサル会社、実行フェーズは各種メーカーやエンジニアリング会社に依頼するケースが当てはまります。
──SMFLみらいパートナーズでは、GHG削減に取り組む企業に対して、どのようなサポートを行っていますか。
永島:当社では、大きく分けると4つのサービスを提供しています。
「脱炭素の計画支援サービス」は、エネルギー使用状況を総合的に把握・分析し、効果的なGHG削減対策の立案や実行までのロードマップをご提供しています。
村上:これまでは下流フェーズのサポートが中心でしたが、現在は、エネルギーの見える化や削減対策立案といった上流フェーズからご相談いただくケースが増えています。お客さまを取り巻く環境や課題などをお聞かせいただいた上で、上流から下流フェーズまで一気通貫でお客さまに寄り添った対応を行っています。
永島:また、「省エネ補助金活用支援サービス」は、省エネ効果が見込める設備更新に利用できる、省エネ補助金活用をサポートするサービスです。
村上:補助金を所管する省庁は、経済産業省、環境省、国土交通省などさまざまなため、各社における対策内容がどこの省庁のどの補助金事業に合致するのか、補助金事業の選定が重要であり、難しいポイントです。
また、補助金事業選定後は、補助金申請に向け、複雑で膨大な申請書を作り込むことになり、日常業務の傍らで対応するのは非常に困難です。当社は、最適な補助金事業の選定を行い、申請から申請後のサポートまでをご提供しています。
永島:「エネルギーサービス」では、太陽光発電によるPPAサービスや熱利用機器による熱エネルギーサービスをご提供しています。
「電力小売代理店サービス」では、当社が複数の小売電気事業者の代理店として、多様なカーボンフリー電力メニューからお客さまのニーズに合ったメニューを選定の上、ご提案しています。当社のPPAサービスと組み合わせれば、電力由来のCO2排出量ゼロが実現できます。
村上:GHG削減対策は多岐にわたるため、お客さまの課題やニーズに寄り添い、削減対策立案から実行まで一気通貫で伴走し、削減実現を見届けます。
永島:「SMFLグループで連携してサポートができる」ことも当社の強みです。
省エネ補助金事業の活用サポートには二つの方法があります。一つは先ほどお話した当社による省エネ補助金コンサルティングのご提供ですが、もう一つは、当社親会社の三井住友ファイナンス&リース株式会社による補助金付きリースのご提供です。リース活用の場合、お客さまは初期投資がかからずに、毎月のリース料金支払いになるため、費用の平準化ができ、補助金の還元により、リース料金が低減できるメリットがあります。
このようにSMFLグループとしてご提供できるソリューションが拡大しております。

──GHG削減に取り組もうとする企業に対する提案で大切にしていることは何ですか。
永島:まずはお客さまが置かれている状況をヒアリングし、お客さま自身も気付いていない課題を浮き彫りにすることから始めています。
それは、GHG削減の取り組みを実行段階に移行しているお客さまであっても同様です。すでに取り組んでいるからといって、いきなりPPAサービスやカーボンフリー電力を提案することはありません。
もちろん最終的にそうしたソリューションを提案することもありますが、大きなアクションを前提とせず、課題に沿った身近な解決策を一緒に探していきます。
村上:例えば、PPAサービスを導入していただいたお客さまには、追加対策として、カーボンフリー電力を採用いただいた事例が参考になるのではないでしょうか。
そもそもPPAサービスを採用いただいても、太陽光発電で賄える電力は電力使用量の一部です。残りの大半は商用電力から供給されますが、GHG削減目標達成のためには、商用電力も見直す必要があります。PPAサービスを採用いただいた後、当社が提案するカーボンフリー電力へ切り替えていただき、太陽光電力+カーボンフリー電力により、電力由来のCO2排出量ゼロが実現できた事例があります。
また、「A工場に太陽光パネルを設置して、使い切れない電力をB工場に送る」という事例もありました。これによってA工場で再エネが導入できるのはもちろん、B工場でも一部再エネ導入が可能になり、大変喜ばれました。
さらに、太陽光発電と一緒に蓄電池を設置することで、休日など、発電した電力を使い切れないときは充電しておき、平日に放電して使用することで、再エネ導入量を増やすことができます。今後の再エネ導入量のさらなる増加には、発電余剰電力の有効活用がポイントになると考えています。
当社としては、各企業さまからより高度な相談をいただくケースが増えているため、GHG削減ソリューションを進化させていきます。
近年、企業による太陽光発電の導入が進んでいますが、これまで以上に太陽光発電を活用する取り組みとして蓄電池を組み合わせた電力貯蔵システムの導入が注目されています。本記事では、蓄電池の歴史から、電力貯蔵システムがもたらす効果、導入・運用時のポイント、蓄電技術の展望まで、リチウムイオン蓄電池などの研究に取り組む是津信行さんに取材しました。
関連記事


──今後、GHG削減ソリューションをどのように展開したいとお考えでしょうか。
永島:現在提供しているエネルギーサービスは、太陽光発電によるPPAサービスをメインとしていますが、今後は太陽光発電以外のエネルギーサービスの展開も拡大していきます。
村上:例えば、熱利用機器による熱エネルギーサービスを展開しています。温水や蒸気などの熱を供給する設備を当社が設備投資し、所有・運用を行い、お客さまには毎月サービス料金をお支払いいただくものです。
永島:オンサイトPPAでの余剰電力の活用促進、蓄電池併設など、サービス拡充に向けた取り組みも行っています。設備の面でも「ペロブスカイト太陽電池」という次世代型の太陽光パネルについての情報収集にも力を入れているところです。
村上:GHG削減ソリューションを進化させて、より多くのお客さまのGHG削減実現のサポートを拡大していきます。
(内容、肩書は2025年3月時点)
文:吉玉サキ/編集:はてな編集部
※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。
※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。
※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。
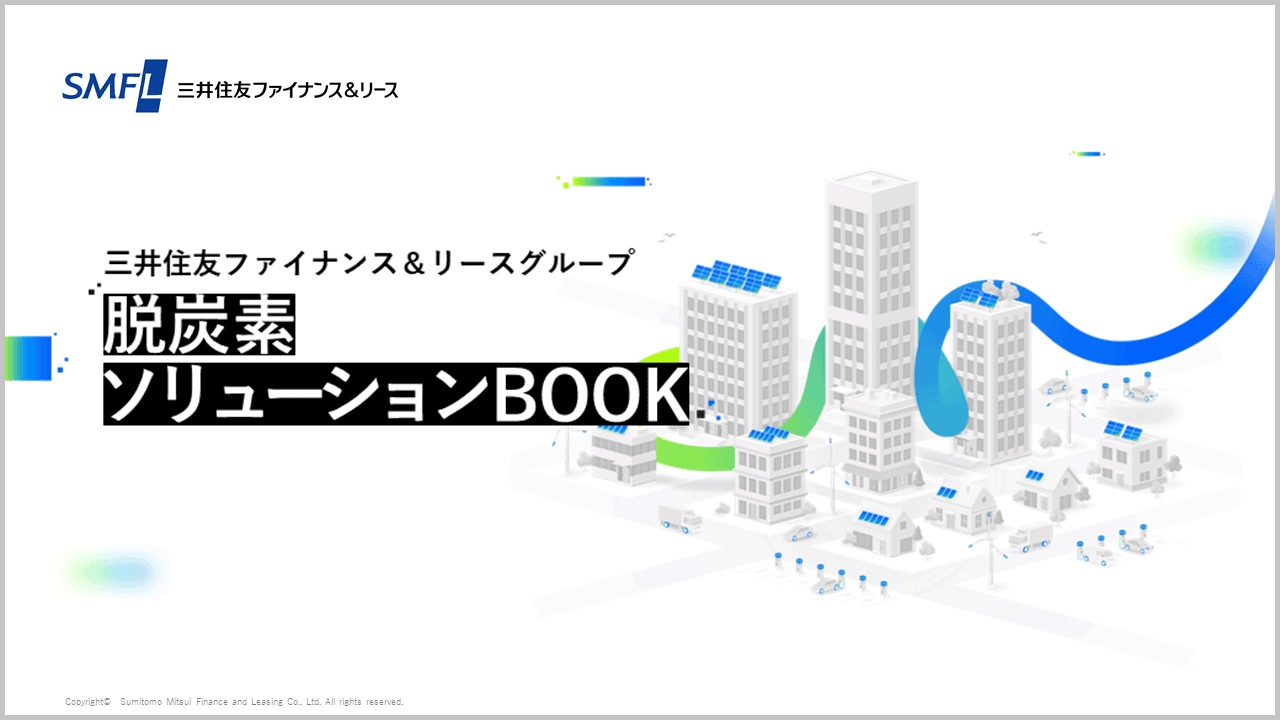
三井住友ファイナンス&リースグループの脱炭素ソリューションを分かりやすく紹介した資料をダウンロードいただけます。
脱炭素実現に向けて、自社に合う具体的なソリューションを探したい方におすすめです。
【個人情報の取り扱いについて】
送信いただいた内容は、三井住友ファイナンス&リースグループ各社にてお問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、商品・サービス情報のお知らせに活用させていただきます。お客さまの同意なしに、回答情報を第三者に提供することはございません。